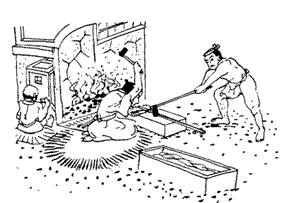 | 1.鍛(きた)える
|
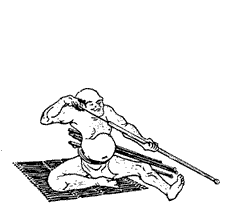 | 2.ひずみを直す
|
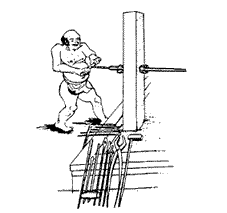 | 3.内側をみがく
|
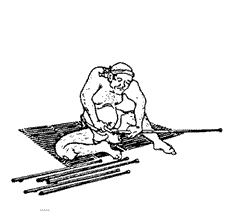 | 4.ネジを合わせる。
|
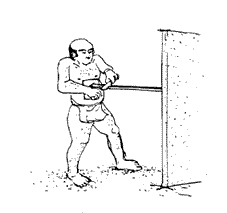 | 5.仕上げる
国友鉄砲は、主に八角形に仕上げられた。 |
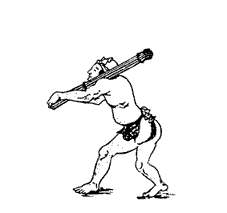 | 6.運ぶ
|
 | 7.銃床の作成
|
  江戸中期 | 8.カラクリの装着(そうちゃく)
|
(挿し絵資料は、八田一氏 原画、「国友鉄砲鍛冶 −その世界−」所収による)
| 国友鉄砲製作の技 |
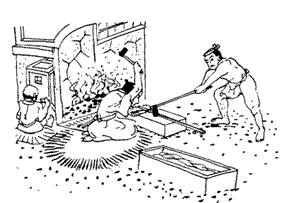 | 1.鍛(きた)える
|
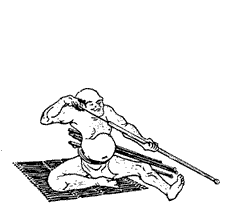 | 2.ひずみを直す
|
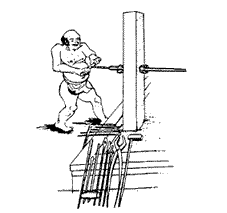 | 3.内側をみがく
|
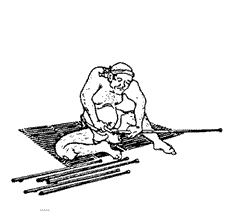 | 4.ネジを合わせる。
|
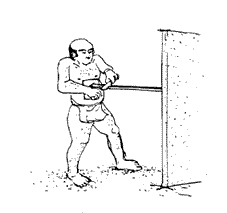 | 5.仕上げる
国友鉄砲は、主に八角形に仕上げられた。 |
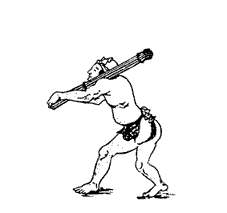 | 6.運ぶ
|
 | 7.銃床の作成
|
  江戸中期 | 8.カラクリの装着(そうちゃく)
|
