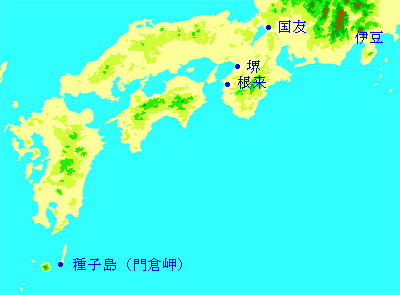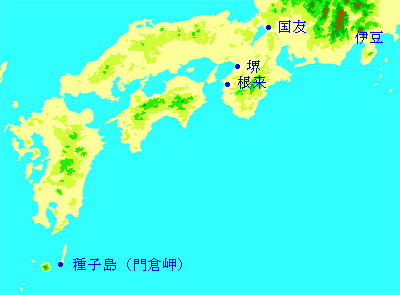新兵器・種子島銃
天文12年(1543)8月、一そうの大きな中国船が暴風雨にあって、種子島(たねがしま:鹿児島県)の南端(なんたん)門倉岬(かどくらみさき)に流れ着きました。
乗船者は、見なれない服装をしており、言葉も通じませんでした。そのため、村の責任者は困りましたが、乗船者の一人に五峰(ごほう)という名の中国人がいて、その人と砂の上に字を書きあうことによって、言葉を通じることができました。そうして、この船にはポルトガル人の商人が乗っており、貿易の目的でやって来たということがわかりました。
(※ポルトガルに残っている資料によると、1542年中国のジャンクが漂着し、中に3人のポルトガル人が乗っていたといいます。「世界新旧発見史」アントニオ・ガルワン:著)
そこで、数日後、乗船していたポルトガル人を島の領主種子島時堯(ときたか1528〜79)にひき会わせました。
このとき、3人のポルトガル人は、それぞれ長さが3尺(約90cm)ほどの重そうな棒を持っていました。中に穴(あな)が通っていて片方の端(はし)はふさがっています。中に不思議な薬をいれ、小さな鉛玉(なまりだま)をそえて置きます。そして、その棒を取り上げて身がまえ、片目をつぶって的をねらって火を放つと、一瞬(いっしゅん)雷(かみなり)のような光りととどろきが起き、みごとに的を射ぬいてしまいます。彼らは、時堯に鉄砲の試し打ちをご覧にいれたのでした。
時堯(ときたか)は、まだ若い領主でしたが、鉄砲の威力(いりょく)にすっかりおどろき、これからの時代に兵器として役立つと思い、2挺(ちょう)の鉄砲を大金で買い求めました。これがいわゆる「鉄砲の伝来(でんらい)」です。
時堯は、ポルトガル人から手に入れた鉄砲をもとに、篠川(ささがわ)小四郎という家来に火薬の調合法を学ばせました。また、数名の鉄工を集めて、鉄砲の造り方を研究させました。しかし、筒(つつ)の底をふさぐ方法がわかりませんでした。これは、ネジを用いる方法で、当時の日本では、このネジの造り方がまだ知られていなかったのです。
しかし、ちょうど次の年にやって来た外国船に鉄工が一人乗っていました。そこで、八板(やいた)金兵衛清定に底をふさぐ方法などを学ばせ、鉄砲を造らせました。その後わずか1年あまりのうちに数十挺(ちょう)の鉄砲を製作することができたといいます。
鉄砲製造の広がり
<国友へ>
種子島時堯(たねがしまときたか)は、ポルトガル人から手に入れた2挺(ちょう)の鉄砲のうちの1挺を薩摩(さつま:鹿児島県)の島津義久(よしひさ1533〜1611)に献上(けんじょう)しました。義久は、それをさらに将軍足利義晴に献上しました。
義晴は、鉄砲に無関心だったようですが、その子の足利義輝は、大変興味を持ちました。そこで、管領(かんれい)の細川晴元(1514〜63)を通じて、近江の坂田郡国友村の鍛冶(かじ)、善兵衛、藤九左衛門を知り、手元の鉄砲を貸し渡して製造を命じたといいます。
<根来(ねごろ)へ>
また、種子島に来島していた津田監物(つだけんもつ)によって紀伊にもたらされ、根来寺杉之坊(ねごろでらすぎのぼう)明算が(みょうさん)が堺出身の芝辻(しばつじ)清右衛門という者に製造させたといいます。
<堺(さかい)へ>
これとは別に、堺の商人橘屋(たちばなや)又三郎が種子島に滞在(たいざい)し、技術を習得して帰り、堺で広めたといいます。
<伊豆へ>
また種子島から出航した船が伊豆に流れ着き、乗船していた時堯の家臣松下五郎三郎によって鉄砲が関東地方にも伝えられたといいます。
こうして、鉄砲が伝来してわずかの間に、近江の国友村、紀伊の根来寺、摂津(せっつ)の堺、伊豆などの各地に鉄砲製作の技術が伝わり、製造が開始されたようです。




This page was last updated on 1998/10/11.
Authorized by Kunitomo teppo no sato Matchlock Museum.
Copyright (C) 1998. by Hideo Hirobe.