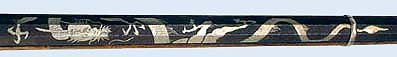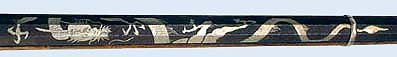| 金工師 国友充昌(臨川堂) |

臨川堂充昌の旧宅 |
国友充昌(みつまさ:1721〜1776)は、多くの国友鉄砲鍛冶の中でも、金工細工(きんこうざいく)の名手として知られています。号は臨川堂(りんせんどう)百棟。通称を丹治といいました。
江戸へ修行に行き、彫刻の技を神田の名金工師・横谷宗與に学び、さらには、奈良彫の技も身につけました。充昌は、きびしい修行に耐え、ついには師をこえるほどの腕前になったといいます。
明和5年(1768)、充昌45歳の時、10代将軍家治は、彼の名声を聞き、刀の目貫(めぬき)1対の製作と3匁玉筒(火縄銃)に竜門の図の彫刻を命じましたが、その出来映えの素晴らしさをほめ、白銀を与えたといいます。
その後、充昌は、修行を終え国友村に帰り、金工師として身を立てましたが、彼の素晴らしい作品を求めて多くの注文があったといいます。
また、充昌は、多くの弟子も育てました。享保以降、文化文政にかけて、彼に技を学んだ楽水堂、姉川堂、永川堂、藍水堂などの人たちが彫金師として活躍しました。
その作品には、竹、虎、花鳥、人物などが写実的に彫られた鐔(つば)が多く、縁頭(ふちかしら)や目貫(めぬき)も残っています。地金には、鉄・赤銅・四分一・真鍮(しんちゅう)などを用いています。また、工法は、薄肉彫や高彫に象眼(ぞうがん)と色絵をほどこしていますが、片切彫や糸透などの技法が用いられた作品もあります。 |
|